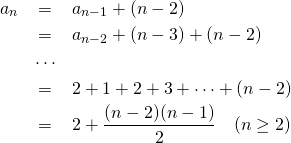古事記~国生み~大八島の国
伊邪那岐命・伊邪那美命は再び国生みを試み、大八島、六つの島々、その他の神々を生むが、火之迦具土神を生んだ時に伊邪那美命は死んでしまう。
大八島
伊耶那岐・伊耶那美二柱の神が天つ神に相談し、その命により鹿の骨を焼いて占い(太占/ふとまに)を行ったところ「女が先に声をかけるのがよくない」
再度島に戻り、天の御柱を左右から回り、今度は伊耶那岐命から先に褒め、島々を産む。
- 淡路之穂之狭別島
- あわじのほのさわけのしま/淡路島
- 伊予之二名島
- いよのふたなのしま/四国
→身一つにして面四つあり - 伊予の国 愛比売(えひめ)
- 讃岐の国 飯依比古(いいよりひこ)
- 粟の国 大宜都比売(おおげつひめ)
- 土佐の国 建依別(たけよりわけ)
- いよのふたなのしま/四国
- 隠岐之三子之島(天之忍許呂別/あめのおしころわけ)
- 筑紫島(九州)
→身一つで面四つ- 筑紫の国 白日別(しらひわけ)
- 豊国 豊日別(とよひわけ)
- 肥の国 建日向日豊久士北泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)
- 熊曾の国 建日別(たけひわけ)
- 伊岐の島
- 天比登都柱(あめひとつばしら)
- 対馬
- 天之狭手依比売(あめのさでよりひめ)
- 佐渡の島
- 大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま)
→天之御虚空豊秋津根別(あめのみそらとよあきつねわけ)
六つの島々
- 吉備の児島
- 小豆島(あづきじま)
- 大島
- 姫島
- 知訶島(ちかのしま)
- 両児島(ふたごのしま)
その他の神々と伊邪那美の死
さらに伊邪那美神は、海・河・水・木・山・野・土・霧・谷・船・食物など三十五柱の神を産む。
最後に火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)を産んだ時、伊邪那美神は女陰を焼かれて死んでしまう。
- 伊邪那岐は伊邪那美を出雲と伯伎(ははきの/鳥取)の国境の比婆の山に埋葬
- このとき伊邪那岐神が十拳剣(とつかのつるぎ)で火之迦具土神を斬首
- 十拳剣から飛んだ血や火之迦具土の死体からも神々が生まれた